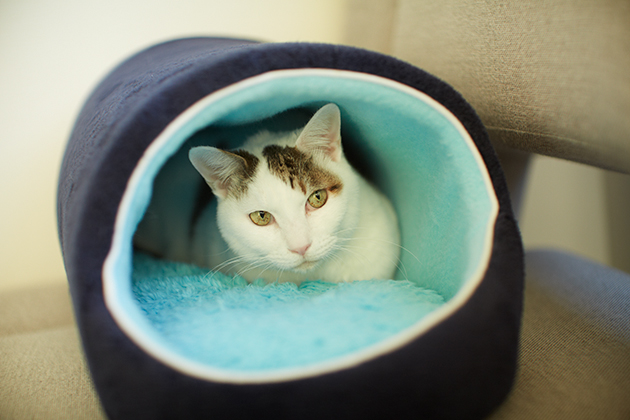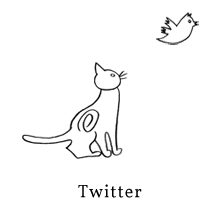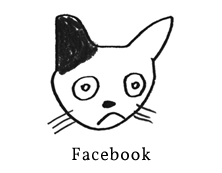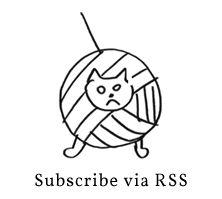小説『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞後、『翼』、『火口のふたり』、『快挙』など話題作を数多く送り出し、最新作では学習障害を持つ子どもたちを教える教師が主人公の長編小説『彼が通る不思議なコースを私も』を発表した小説家の白石一文さん。30歳を過ぎて、猫と暮らし始めたという白石さんの家には現在、4匹の個性的な猫たちがいます。「飼い猫こそが理想的な生命体だ!」という白石さんに、猫と人間の関係について伺いました。
忽然と現れた猫たち
ー猫と暮らすことになったきっかけは?
「母親が動物が嫌いで、ずっと犬や猫に接する機会がなかったんです。30歳を過ぎて、はじめて猫に出会ってしまった。当時、僕は出版社で働いていたのですが、会社近くの駅で、捨てられた子猫を見つけてしまい、それまで猫に触ったこともなかったのにもかかわらず、このまま置いていったら死んでしまう、どうせ死ぬならウチで死なせてあげようと保護したんです。ところが、そうやって悲壮な気持ちで連れて帰ったらあっと言う間に元気になってしまい、そのまま飼うことに。チビという、とっても頭のよい雌猫でした」
ー突然、猫がやってきて、大変ではなかったですか?
「いや、最高ですよ。仕事をして夜遅く帰ってきても、チビは必ず玄関まで迎えに来てくれる。もうメロメロです。しばらくして、会社に行く途中で、今度は黒猫を拾ったんです。名前はクロ。当時は一軒家に住んでいたので、ときどき外に出していたんですが、ある朝、家の前の道路でタクシーに轢かれて亡くなってしまった。生涯であんなに泣いたことはないというほど悲しかったし、守ってやれなかった自分が情けなくて、クロに申し訳なくてどうにかなりそうでした。そのあと、僕は家を出てしまい、チビは置いてきたのですが、15歳まで立派に生きて、最近亡くなったと去年息子から来た手紙で知りました」
「今一緒に暮らしているかみさんの良子は動物にはあんまり興味がなく、僕も会社を辞めてからは引っ越しが多くなってしまったので、もう猫は飼えないなと諦めていました。そんな時、くうちゃんと出会ってしまったんです。以前住んでいた博多の団地の近くに散歩コースにしていた大きな公園があって、そこはコンクリートに囲まれた未来的な雰囲気の場所で、野良ちゃんなんて一度も見かけたことはなかったのですが、なぜかその日は東屋のテーブルの上に猫がポツンといて。どうやって来たのかもわからないのですが、奇妙な光景というか、ちょっと神々しかったですね。近づいても逃げないし、ガリガリに痩せていたので、連れて帰ることにしたんです」
ー猫が居るような場所ではないのに、不思議ですね。白石さんのことを待っていたのでしょうか。
「忽然と出現したんですよ。でも、猫との出会い方ってそうじゃないですか? ほかの猫たちもみんな、いきなり僕の前に現れたんです。くうちゃんを飼い始めて、1年くらい経ったある日、かみさんが当時バイトをしていた児童養護施設で野良ちゃんが子猫を生んでしまい、里親を探すためにうちで預かることにしたんです。母猫と合わせて合計6匹。気合で里親さんを探して、最後に残ったのがミナちゃんでした。もともと母猫のマイちゃんと子猫の内の一匹は自分で引き取ろうと思っていたので、うちで飼うことに。ただ母猫のマイちゃんとくうちゃんが、ずっと仲が悪くて、マイちゃんをぜひにという知り合いがいたので、そちらで飼われることになりました。それからしばらくは2匹だったのですが、また見つけてしまったんです。神楽坂の駐車場にいた、汚れた姿をしていた翼くん。さらには、かみさんがTwitterで見つけた、保健所へ連れていかれる寸前だった黒猫のとらりん。とらりんは当時住んでいた神戸から新山口まで新幹線で引き取りに行きました。いまはこの4匹の猫たちと暮らしています」
ーずっと動物と暮らしてこなかったのに、30歳を過ぎて急に猫まみれになったのですね。猫が飼いたくて飼い始めた人とは違い、偶然出会ったわけですよね。
「最初に拾ったチビもそうですが、私を拾ってくれるの? って訴えかけてくるじゃないですか。いのちをかけた訴えだから拾うしかなくなるんですよね。って言いながらも、でも明らかに、猫は僕と性が合っていたんです。いままで55年間も生きて来ましたが、生まれてよかったと思えるようなことなんてほとんどありません。僕が、ああ生まれてきてよかったなあ、って心底思えるのはたった2つだけ。ひとつは甘いモノを食べられること。そしてもうひとつは猫と出会えたことです。こんなにたくさんの猫たちに囲まれているのは、ここ7〜8年のことですが、猫を見る度に、生まれてきてよかったかもしれないって感じます」
ーそれは愛猫たちを見てということですか? ほかの猫を見ても同じように感じるのでしょうか。
「猫種全体ですね。“猫族”と言ってもいいかもしれない。笑われるかもしれませんが、もしも自分がこの世界の支配者になれたら絶対に「猫法」というものを作ろうと思っているんです。猫法の第一条は、〈世界中の猫は全部白石一文のモノである〉(笑)。世界中の猫は僕の所有物であり、猫を飼っている人たちは僕の猫を一時的に無償でレンタルしてもらっている立場に過ぎないわけです。だから、その僕の大事な猫たちに対して彼らや、周囲の人たちがひどいことをしたら、すぐに警察の猫課の刑事が駈け付けて捜査し、犯人は逮捕される。彼らは当然厳罰に処されることになる(笑)」
ーなんと(笑)。そこまで猫を特別扱いする理由は?
「猫は見た目からしぐさまで、すべてが可愛い。だから何をしてもいいんです。僕は親も作家だったし、子供の頃から病弱で活字の世界の中でずっと生きてきました。だから文字というものを掛け値なしに神聖視している人間です。文字を粗末にするのが一番嫌い。今でも本や雑誌を買う時は、結束して紐の跡がついていたり、カバーが汚れていたりするのを買うようにしている。活字の載ったものがそうした理由で捨てられてしまうのが本当に嫌なんです。だから文字に何かを載せたり、文字を踏んだり、何かをこぼしたりされるとすごく怒ってしまう。まして自分の原稿の上にかみさんが何かこぼしたりしたら、もうすごい剣幕です。でも、猫だけは例外なんです。猫たちが原稿の上に乗ってもまったく腹が立たないどころか、何か縁起のいいことのようにさえ思ってしまう(笑)。要するに猫のすることなら、すべてが許せてしまうんですよね」
生命体として理想的な飼い猫の暮らし
ー猫は言葉を理解していると思いますか?
「猫は人間の感情を読むことが出来るし、猫自身も感情を持っている。もちろん理解していると思います。言語化しているかどうかが、人間と動物との大きな違いですよね。言葉にする前の気持ち、例えばそれをカップに注ぐ前のスープの状態としたら、これが何々のスープであると知るためには、まずはカップに入れ、ラベルを貼って種類分けをしていく必要がある。喜怒哀楽といったような人間が感情と思い込んでいるものはそうやってすでに仕分けされたもののことですよね。でもそういう識別をする前のスープそれ自体、つまりおおもとにあるものこそが感情の本体だし、そういう本体は人間だけでなく、もちろん猫にも他のさまざまな動物にも確実にあるのだろうと思いますね」
「人間は感情過多です。何かに対して愛情や憎しみなどを注がないと生きていけないようにできている。感情発生装置である大脳が大きくなりすぎてしまっているんですね。だから、どうしても我が子やペットに対して過剰な愛情を注いでしまう。子離れできない親なんて、生き物の習性としてはおかしいですよね。でも、そこが人間の素晴らしいところでもある。自らの感情を生涯もてあまし、愛や孤独に一喜一憂し、死ぬときは悲しくて悲しくて、そういう死の恐怖を乗り越えようとさまざまな信仰や信念を編み出していく。死後の世界を本気で想像したりもする。そんな動物は人間だけです。そして、その溢れ出てしまう過度な感情を思い切りぶつける大きな対象の一つが猫であり犬なんだと思いますね。とはいえ、いくらボールを投げても、受け取るミットを持っていないと一方通行になってしまいます。何千年も猫や犬との関係が続いているということは、彼らは確かにそのミットを持っているんですよ。人間の感情を、言葉でなくとも、受け止めることができる能力が彼らにはちゃんと備わっている」
ー今はペットの数が、子どもよりも多いという統計もありますよね。飼われるペットの立場では、この状態をどう感じていると思いますか?
「飼い猫たちにとっても、人間との共生は猫人生の理想型に近いと思います。過剰な愛情を注ぐ巨大な存在がいて、頼んでもいないのに何から何まで世話をしてくれる。彼らは、食べて、排泄して、寝るだけ。まさに天国ですよ(笑)。飼い猫の場合、ずっと部屋に閉じ込められて自由がないんじゃないかと心配する人たちもいますが、僕はそうは思いません。自分のすぐそばに無償の奉仕をしてくれる人がいて、生存が保証され、一生、遊んで暮らしていける。生命体の中でも、飼い猫が最も幸せなんじゃないかと思います」
ーでは白石さんは、生まれ変わったら飼い猫になりたいですか?
「もちろんなりたいですね。こんなに気持ちのよいことはないですよ。飼い猫の寿命は20年近くあります。野良猫はそれよりずっと短いし、ライオンやヒョウもそんなに長くは生きられない。どれだけ、飼い猫の生き方が楽かということですよ。幸せや�
実感というものは、やはり誰かに守られ、愛されていると感じるときに最も強く得られるものです。ストレスがないとつまらないと世間ではよく言いますが、そのストレスの先に得られる�
実感を、ストレスがない状態で手に入れられるとしたら、ストレスなんてそもそも必要ありません。飼い猫はずっと、そのあたたかな�
実感の中にいる。そして猫という種は、何千年かの時間をかけ、その最高の仕組みを人間を利用することで実現したわけです」
ー逆に人間は、猫といることでどんなメリットがあるのでしょうか。
「人間はとにかく行き場のない過剰な愛情を猫に受け止めてもらえるだけでいいんです。受け止めてくれるから、猫という動物を選んだのだと思います。人間関係だけですべてが満たされればよかったのですが、人間同士のつながりは複雑で、利害も絡んでくるし、愛情だけでなく憎しみも生まれてしまう。愛情だけのはけ口が必要なんです。何かコレクションしたり、アイドルの追っかけをするのも同じですね。その中でもペットいうのは、直接、生の愛情を受け止めてくれるからより人間にとって重要な存在なんでしょう。進化という面でいえば、猫のほうが人間よりずっと先をいっているのかもしれませんね」
ー人間は働かなければいけないですよね。猫のように寝て、食べて、遊んでいるだけでは、暮らしてはいけない。
「自分たちは頭がよくて万物の霊長として世界を支配しているなんて人間は錯覚していますけど、大体そういうふうにいい気になっているときって誰かに巧みに騙されていますよね(笑)。犬とのあいだには主従関係があり、犬は人間に尽くす存在ですが、猫はそういう明らかな貢献は何もしない。その点では、彼らは人間の心を支配している。要するに僕たちを虜にしているわけです。猫が人間を支配していると考えた方が分かりやすいような気がします(笑)」
物語の中にいる猫
ー新刊『彼が通る不思議なコースを私も』では、主人公が普通の人が気づかないオーラや気配を読み解くことができますよね。猫にも独特の気配があると感じますか?
「猫って気配を消すことができる。つまり気配というものが存在することを彼らは証明してくれるわけです。フッと見たらそこにいる。そして、猫は、人間とは全然違う何かを見ている気がします。僕たちには彼らに見えるものを見ることができませんが、その一方で、人間にしか見えない世界というのもあると思います。たとえばオーラというのはよく色で分けられますが、そうやって詳細に色分けするというような認識法は人間にしかできないことかもしれないですね」
ー白石さんは「つくみの記憶」「七月の真っ青な空に」など、猫を題材にした短篇も書かれていますが、物語の中では、猫と人との関係だけでなく具体的な保護活動についても触れていますよね。
「僕は、人間と動物との関係をそろそろ本気で変えていかなければいけないと思っています。生物を大量に生産・管理し、まるでモノのように彼らのいのちを奪って食べている。まさに生物工場という側面がある。こういう繁殖と生存への人類のアプローチはきっと過渡的なものでしかないのだろうと思います。いずれ、動物のいのちを奪うことなく、我々は高カロリーの食料を調達できるようになるでしょうし、そういう意味では、食物連鎖のくびきから完全に解放される日が訪れるでしょう。家畜という存在もやがてテクノロジーの力でなくしていくのではないでしょうか? 我々日本人に馴染みの深い仏教では肉食を禁じている宗派があります。釈尊はおそらく動物の肉は食べなかったでしょうが、なぜ彼は肉食をしなかったのか? 最近、その理由についてよく考えています。『つくみの記憶』には、人間になった猫が出てくるんですが、そういう化身という発想は、案外、この世界を理解するうえで重要なもののような気がしています。というわけで、いずれ動物と人間との関係について、霊的な側面も含めた小説を書いてみようと考えているんです」
ー「つくみの記憶」では、亡くなった白猫が人間のつくみとして現れて、主人公はそのしぐさや性格に魅了されていきますが、猫のような人というのは理想なのですか?
「猫みたいに、美しく自由奔放で、いきなり木に登ったりする女性がいたら、あっと言う間に好きになってしまいますよ」
ー猫のしぐさを見ているだけで、人間側の動作がすべて止まってしまうというような描写があったのですが、こうやって取材している間も、猫のことはついつい見てしまいますよね。
「赤ちゃんも同じですよね。その場にいる全員が、赤ちゃんの一挙一動に注目してしまう。何をするわけでもないのに、見ざるを得ない特別な輝きがあるんです。猫のことは憧れとして見てしまうんです。猫自身は自覚していないかもれないけれど、誰かと比較して得られる幸福感とは異なる絶対的な幸福感を彼らは手に入れているような気がします。だって、これだけの愛情を注がれて、怒られることもないわけですから」
ー猫がいたずらをして怒っても、何度か繰り返すうちに、人間側がもういいかって諦めてしまうことが多い気がします。
「こちらの言う事は断じて聞いてくれないですからね(笑)。人間同士だったら友達がいなくなってしまうかもしれない。それでも一緒にいたいと思える魅力があればいいですが、人間は猫ほど可愛くないから無理でしょう(笑)。また猫は自由なところがいいと言われますが、自由であることよりも、愛情を注がれることのほうが大事です。僕が猫たちを愛するように僕を愛してくれる人間はきっといません。人間同士だと、いくら愛されても、その分を返さなければいけない。もちろん猫も返してくれてはいるのですが、返そうと思って可愛い仕草をしているわけではない。猫はただ、存在しているだけでいいんですよね」