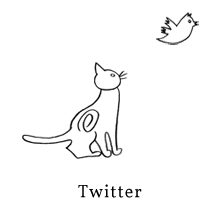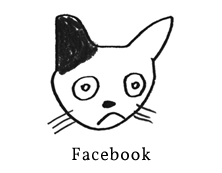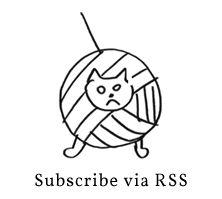小説『リトル・バイ・リトル』『ナラタージュ』など数多くの作品を生み出してきた作家の島本理生さんは、6歳の雄猫たびさんと暮らしています。病気がちだったというたびさんは、いまや何事にも動じない貫禄のある姿を披露。また、10月26日に発売する『ilove.cat』書籍版へ寄稿していただいた、猫をテーマにした短篇小説「猫を探しに来た」のお話もうかがいました。
頼りない猫がやってきた
—たびさんとの出会いは?
「インターネットの里親募集の掲示板でみつけて会いに行きました。はじめは雄猫を希望していたのですが、途中で、鼻水を出してよたよたした頼りない子が寄ってきたんです。一緒に行った母のほうが “おとなしくてかわいいからこの子にする!”と即決して(笑)、連れて帰ることになりました。名前は、上から見た姿が草履に似ていたので、〈ぞうり〉にしようとしたら、母に変だと言われて、履物つながりで〈たび〉になりました。偶然ですが、後からこの子の柄をタビー柄(縞柄)と呼ぶことを知ってびっくりしました」
—猫を飼うのは初めてだったのですか?
「実家でも、祖父母の家でも飼っていました。でも子どもの頃に飼っていた猫はすぐに病気で亡くなってしまい、また飼うことには抵抗があったんです。一人暮らしするようになって、ようやく飼いたくなりました。ずっと家で原稿を書いていると、息が詰まることがあって、そういう時に猫がいたらいいなと。同じ空間にいるんだけど、何か別のことをしている。気ままな猫がいる暮らしって、素敵なんじゃないかなと」
—実際にたびさんと暮らし始めて、何か変化はありましたか?
「想像と全然違いました。猫って、もっと独立した生き物だと思っていたのですが、雄猫のせいかベタベタ甘えてくるんです(笑)。病気がちで、つきっきりで看病していたせいもあって、大人になっても基本的に甘えん坊ですね。原稿を書いていても机に乗ってきたり、邪魔をするので、膝の上にのせて仕事をしています」
—好きなおもちゃはありますか?
「スズランテープくらいですね。あとは、リボンやはりがねの猫じゃらしとか。最初の頃は色々買ってあげたのですが、もともとあまり活発なほうじゃなくて、遊んであげようとしても、5分くらいで息切れしています(笑)。布も好きで、人が履いているジーンズにガリガリすることもあります。あとは、ソファーで爪研ぎするくらいですね。爪研ぎは廊下や台所など何ヶ所か設置しています」
—ごはんやトイレのこだわりは?
「『ヒルズ』のカリカリとウエットを混ぜて、少しずつ小分けにしています。一度にたくさんあげると、あるだけ食べてしまって、具合が悪くなったりするので。トイレは階段の下の物置がぴったりだったので、扉に猫の通り穴を空けて置いています。砂は流せるタイプです」
—集めている猫グッズや、愛読している猫の本や漫画は?
「猫だけでなく動物モチーフのアイテムは好きで、鳥や鹿などのオブジェも集めています。大島弓子さんの『サバの夏が来た』が大好きで、生活をともにしている感じがとてもリアル。四季折々の暮らしと猫の描き方が素晴らしいんです。小説では、江國香織さんの『ホリー・ガーデン』ですね。主人公が朝帰りをした時、足下で文句を言う猫を抱き上げてなだめたりするシーンがあるんです。特別な存在というよりは、生活の中で自然に共生している感じが好きですね。緒形もりさんの『うちのうめは今日もげんき』は、作者がアライグマ・犬・うさぎを飼っていて、最後のほうに猫を飼うんです。その猫が健気でかわいくて、作者の愛情を感じます」
猫への接し方でみえる人間性
—小説を書く時、猫はどういうモチーフとして登場することが多いのですか?
「たびと暮らしはじめる前は、動物を登場させる時には少し身構えるというか、特別な意味をもたせることが多かったんです。でも今は毎日一緒にいるので、逆に自然に出てくる。同じ猫でも、ユーモラスに描いたり、人間の犠牲となる存在だったり。書き方のバリエーションが増えた気はします」
—『大きな熊が来る前に、おやすみ。』に掲載されている小説「猫ときみのとなり」では、猫への接し方により登場する人物の性格を描いていますよね。これは実体験に基づいているのでしょうか?
「そうですね。猫だけでなく、動物への接し方で、どんな人かわかる時はあります。すぐに懐かれる人もいれば、ちょっと性格的に雑な人の前では、猫が怖がって逃げてしまったり。相手の繊細さや優しさ、あるいは真逆の部分が、猫を通して見える時があります。人間同士であれば、あの人は雑なタイプだけどいいところもあるよね、と複合的に解釈したり、嫌なところは見ないふりをしたりもしますよね。でも猫は自分にとっていい人、悪い人というのを一瞬で直感的に判断してるんだな、と。逆にうちに来てすぐに猫が膝の上に乗って懐くような人もいて、どういう人は、やっぱり穏やかな人が多いですね」
—あの小説では、動物病院での飼い主のふるまいに対してやや不信感があるような描写がありました。
「動物をどういう存在と捉えるか、というのは難しいテーマですね。人ではないかからと、ひどい扱いをすることには憤りを覚えますが、やたらと特別扱いして考え方が極端になりすぎるのことには、疑問を感じることもあります。里親募集サイトを色々調べていた時にわかったのですが、そういった考え方の違いによる飼い主どうしのトラブルがけっこう多い。猫を飼い始めてから、そういう世界を知ったので、自分がどちら側というよりは、問題提起する形で一度、小説で書きたいと思ったんです」
猫という“特別”ではない存在
—今回、ilove.catの書籍版『ilove.cat』では猫をテーマにした短篇小説「猫を探しに来た」を寄稿いただきました。
「実は、SFというか、擬人化した猫が登場するお話を何本も書き溜めているんです。猫はどちらかというと、ファンタジーのような描き方がしやすい動物なのかもしれません。何を考えているかわかりづらいからこそ、すごくやさしい存在にしたり、わがままにもできる。モチーフとして描きやすい。今回はちょっと突飛ですが、猫が食用になっている近未来の世界での話を発表することにしました。以前、小説に書いた、子どもが捨て猫を拾って来てまた捨ててしまうという話に、すごく怒る愛猫家の方がいたんです。私自身は子どもの行為を否定的に書いたつもりだったのですが、それでも書いたこと自体を批判されて。その時に猫という存在について、今一度、考えてみようと思ったんです。自分は、猫を愛する一方で、無頓着に牛や豚を食べて生きている。特定の生き物だけを当たり前のように特別扱いすることについて、この機会に見つめなおしてみようと」
—猫だから特別、というわけではないと。
「やみくもに愛してしまいがちなところを、少しだけ落ち着いて見ていこうかな、と。そして、きちんと要求を理解した上で、上手く付き合っていけたらいいですね。とはいえ言葉がわかるわけではないので、調子が悪い時はできるだけすぐに気づくように気をつけていますが、こちらが忙しい時にワガママを言われると、適当にあしらってしまうこともあります(笑)。ただ、猫って演技をするんですよね。旅行から戻って、実家にたびを迎えに行くと、平気な顔をしているんです。“じゃあ荷物が多いから、いったん帰ってまた後で来るね”と帰ったら、“ドアにすがりついて鳴いているからすぐに戻って来て”と弟から電話がかかって来たことも。もっとわかってあげなくちゃいけないな、と再認識した出来事でした」
—たびさんにとって、島本さんはどういう存在に見えているのでしょうか。
「どうでしょう。上下関係があるのか、自分が上だと思っているのかわからない。そこが猫の面白いところだと思います。たまに下手にでたり、敏感に察知している。落ち込んでいる時は、遠くからじっと見守っていてくれたり。そういう面に触れると、本当に繊細で優しい動物だなと感じます」